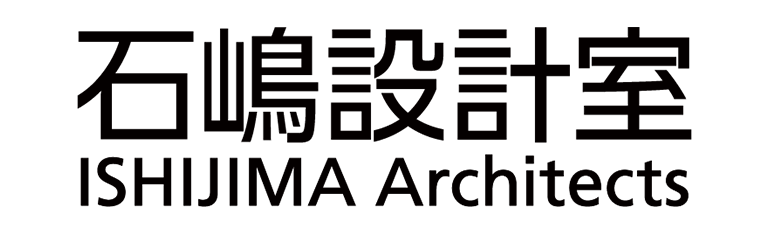文部科学省の2013年度学校保健統計調査速報にとると、福島県では肥満化傾向の子どもの割合が増加しているが、これは福島第一原発の事故以降の外遊びの制限にともなう運動不足や生活習慣の変化等が原因であると言われています。
このような背景を踏まえ、この園舎では子どもたちが安心して「汗をかける幼稚園」をつくることを目指しました。それは屋外での活動を補完するための体育館のように囲われた大空間をつくるのではなく、あたかも屋外にいるかのような「開放的な半屋外空間」をつくることです。
また、計画地の周辺には総合病院や保健所等、医療・福祉系施設が多く立地しており、来街者は多世代に渡ります。さらに計画地の北側には同じグループの医療法人社団が運営する介護老人保健施設が隣接してました。
このような状況から、かなや幼稚園では「汗をかける幼稚園」と「交流できる幼稚園」の 2つをテーマに掲げ設計を行いました。
「汗をかける幼稚園」。それは屋外での活動を補完するための体育館のように囲われた大空間をつくるのではなく、あたかも屋外にいるかのような「開放的な半屋外空間」をつくることです。
「交流できる幼稚園」。それは高齢者と子ども、その家族、さらに地域の住民など多くの方が交流しふれあうことで、高齢者には活力の源となり、子どもや保護者には地域に伝わる伝統や昔からの遊び、子育ての知恵などの継承が行われる多世代間の交流が生まれる園舎をつくることです。
逆L字型の敷地の交点に園舎を配置することで、道路側には地域に開放したパブリックな前庭、奥にはプライベートな園庭の2つの性格の異なる園庭をつくりました。
園舎は3つのゾーンで構成しました。中央には室内遊戯場、開放的な河川側には保育室、道路側には管理諸室や預かり保育室を配置しました。
膜屋根で覆い、軟らかな自然光を採り入れ「開放的な半屋外空間」とした室内遊戯場には、2階の回廊をはじめ、滑り台やクライミングウォール等、様々な遊び要素を挿入しました。
一方、保育室や管理諸室等は、ルーバー状の梁を現し、落ち着いた雰囲気としました。
構造は木造の在来軸組工法を採用しました。膜屋根は、遮蔽物で透過性を損なわないよう注意して、膜の透過性と木の暖かみを併せ持ちった優しい空間を実現しました。
設備は2つの特徴があります。1つ目は地中熱を利用した室内遊戯場の自然換気設備、2つ目は保育室の床吹出しの空調です。いずれも空調に頼りきらない、子どもの身体が持つ体温調節機能を促進する室内環境を目指しました。
室内遊戯場の照明は、保育室や2階から溢れ出る光で生き生きとした活気のある空間を生み出しました。一方、保育室はルーバー状の梁の間に光源を設置するとともに、活動にあわせて光のシーンを切り替えられるようにしました。
夜間には、膜屋根を通して屋外へ暖かく溢れ出し、自然なライトアップとなるように目論みました。
| 計画地 | 福島県いわき市 |
|---|---|
| 用途 | 幼稚園 |
| 定員 | 70人(2014年4月現在) |
| 敷地面積 | 1,642.65m2 |
| 建築面積 | 661.99m2 |
| 延床面積 | 763.99m2 |
| 構造 | 木造、一部鉄骨造 |
| 階数 | 地上2階建 |
| 受賞 | 第35回東北建築賞特別賞/第32回福島県建築文化賞優秀賞/2016年日本建築学会作品選奨/第8回キッズデザイン賞奨励賞/グッドデザイン賞2014/子ども環境学会賞デザイン奨励賞 |
| メディア掲載 | 「木の国」日本の新しい空間技術/ja96 YEAR BOOK 2014/新建築2014年6月号/School Amenity 2014年6月号/近代建築2014年6月号 |